メタンハイドレートは溺れる者のつかむ藁ではない (2)
米国が1960年代にはメタンハイドレートの採掘研究に着手しておきながら、長期的なエネルギー開発計画のままにしており、2015年にようやく小規模な採掘実験を行う計画であるのは、まさにこうした環境や生態への危険性のためだ。
技術上のボトルネックは採掘の障害の1つに過ぎない。開発コスト面から見て、メタンハイドレートが経済効率的に石油や天然ガスに比肩しうるかどうかも疑問だ。メタンハイドレートの放出する気体は体積が大きく、輸送が極めて困難で、海底パイプラインを建設するか液化する必要があるため、採掘だけでなく貯蔵・輸送コストも相当高くつくと専門家は指摘する。こうした障害は短期間には解決困難だ。
エネルギー面の苦境を脱しようと焦る日本の気持ちは理解できる。だが科学技術は客観的法則を尊重しなければならない。焦っても問題の解決にはならない。原子力の利用において「安全上越えてはならない一線」を克服することのできなかった日本が、メタンハイドレートというさらに不確定性の大きいエネルギーの利用において、さらに深刻な生態と環境への危険を前に、どうして安易に楽観的になることができるのだろうか?
エネルギー問題は確かに現在世界が金融危機の暗雲を脱するうえで肝要だ。蒸気機関の時代は石炭を利用し、内燃機関時代は石油や天然ガスを利用した。未来の時代に「新エネルギー」が必要なのは確かだ。だがメタンハイドレートは明らかに違う。本質的に、別の形の天然ガスに過ぎないのだ。
技術、コスト面の難題を克服すれば、メタンハイドレートは人類にもう1つのよりクリーンな燃焼エネルギーをもたらすかもしれないが、技術革命をもたらすことはできない。画期的な技術革命がないなら、いかなる「新エネルギー」も水泡であり、「旧経済」の延命に過ぎず、真の「新経済」を切り開くことはできない。
筆者が繰り返し強調してきたことだが、食料の採集から食料の生産へと移った農耕文明は人類にとって大きな技術的躍進だった。同様に、核分裂から核融合へと移り、人類の科学技術を微粒子のレベルにまで深化し、化石資源の採集から物質のミクロ構造と分子運動の分析を通じたその法則の把握へと移り、さらに「エネルギーの生産」へと移り、「再生エネルギー、永続的エネルギー」を真に実現する。これこそが人類にとって偉大な飛躍的技術進歩だ。
本質上、石炭、石油、天然ガスといった「古いエネルギー」と光エネルギー、風力エネルギー、バイオマスエネルギーを含むいわゆる「再生可能な新エネルギー」は、いずれも広義の太陽エネルギーだ。そして太陽エネルギー自体が核融合によるエネルギー放出の1つの形なのだ。制御核融合は人類の掌握できる真の「無限エネルギー」であり、人類の技術進歩と文明の高度化の主流の方向性、未来の終着点を代表するものでもある。この技術革命を月開発プロジェクトや深宇宙探索プロジェクトと結びつければ、人類の文明は飛躍的な高度化を実現し、「地球人」は「宇宙人」に進化する。











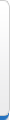
 関連記事
関連記事 夫婦の顔を交換 いたずら写真
夫婦の顔を交換 いたずら写真 海南航空で航空セキュリティー要員を募集
海南航空で航空セキュリティー要員を募集 裕固族の伝統的婚礼
裕固族の伝統的婚礼 フィギュアスケート世界選手権 金妍児選手が優勝
フィギュアスケート世界選手権 金妍児選手が優勝



