PRISMスキャンダル:「例外論」は国際関係のモデル転換にとって障害
「PRISMスキャンダル」は機密漏洩事件の引き起こした政治的動揺であり、生々しい国際政治の講義でもある。
「PRISMスキャンダル」は「重大な影響力を持つ強国の打ち出す多くのルールには、他国のみに押し付けて自国は守らないものが少なからずある」という国際関係に古くから存在する問題を再び暴露した。ロイター通信は「過去15年間ですでに世界は変化したが、米国例外論はかなりの程度において変わらぬままだ」と鋭く指摘した。
周知のように米国はルールを定めることが好きなうえ、こうしたルールに普遍性という後光を添えることに熱中する。だがルールの効果には常に正負両面がある。他国を規制し、非難するのにも使えるが、自らの行動の幅を狭めることにもなる。米国にとって後者は現代の国際関係システムの多くの分野における自らの特殊な地位と構造的に矛盾し、国際問題の処理におけるその政治的論理や行動様式とも合致しない。ロイター通信の指摘する米国例外論が変わらない深層の原因はおそらくここにある。
特殊な存在として振る舞うことが歓迎される可能性は低く、大々的にそうすれば圧力は一段と増す。米国は強大な技術力によって「ステルス例外」の余地を切り開いた。
米同時多発テロ発生後、米国の心理状態は大きく変化し、国際問題の処理を焦るようになった。万事悠然と構えていては、テロとの戦いは拡大する。米国の情報収集当局は全てを対象とし、全ての場所に存在する膨大なシステムへと急速に変化、発展した。それは米国人の日常生活の中に浸透し、世界各地にまで伸び広がった。ハッキングは合法的な情報収集方法となり、FBIはどんな対象でも好きなように監視できるようになった。





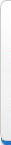







 関連記事
関連記事
 米「プリズム」暴露のスノーデン氏のモデル志望時期の写真
米「プリズム」暴露のスノーデン氏のモデル志望時期の写真 キム・テヒの9年前の写真
キム・テヒの9年前の写真 動物の頭に人の体の彫像
動物の頭に人の体の彫像 第9回中国(北京)国際園林博覧会
第9回中国(北京)国際園林博覧会



