日本政府「デフレなくなりつつある」緩和政策強化?
日本政府は15日に8月の月例経済報告を公表し、日本はデフレ状況ではなくなりつつあるとの見方を示した。これについてアナリストたちは、第2四半期(4-6月)の国内総生産(GDP)成長率は2.6%にとどまり、市場の期待に及ばなかったこと、また日本経済に対する市場の楽観的な見方がトーンダウンしていることから、日本銀行(中央銀行)が下半期も引き続き緩和政策を強化すると予測する。「経済参考報」が伝えた。
▽エネルギー価格が物価押し上げ
同報告によると、日本経済は今、着実に持ち直しており、自律的回復に向けた動きもみられる。個人消費は持ち直し、生産は緩やかに増加し、輸出は持ち直しの動きがみられるという。
また同報告によると、最近の物価の動向を総合してみると、デフレ状況ではなくなりつつある。7月の月例経済報告では、デフレ状況は緩和しつつあるとしていたが、8月はより楽観的な見方に変わった。だが日本の政府関係者によると、今、日本はデフレから脱却したと言うのは時期尚早だ。政府は消費者物価指数(CPI)が上昇局面になり、下降しなくなるまでは、デフレ脱却の最終的な結論を下すことはできないという。
日本は公債総額が巨額だが、大規模な経済喚起措置を打ち出しており、2年以内に2%のインフレ目標を達成したいとしている。ここからわかることは、日本政府はデフレ脱却を最優先の目標とし、財政の持続可能性を2番目に置いているということだ。
CPIは日銀がインフレを測る際に最もよく利用する指標であり、経済の回復ぶりを判断する重要な根拠でもある。最新のデータによると、今年6月には価格変動が大きい生鮮食品を除くCPIが前年同月比0.4%上昇し、14カ月ぶりに上昇に転じた。だが多くの分析が指摘するように、日本の現在の国内物価水準の上昇は主にエネルギー価格が後押しするもので、消費ニーズが高まったわけではない。大幅な円安で輸入コストが上昇し、特に原子力発電に代わるものとして輸入されたエネルギーの価格が上昇し、企業はコストを消費者に転嫁した。このため物価上昇局面となったのであり、経済の活力が増したわけではない。
同報告は日本の雇用情勢に対する見方を修正し、雇用情勢は改善しているとした。最新のデータによると、今年6月の失業率は前月の4.1%から0.2ポイント低下して3.9%になり、2008年10月以降ではじめて4%を割り込んだ。景気回復にともない、企業の求人も増加している。





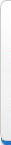

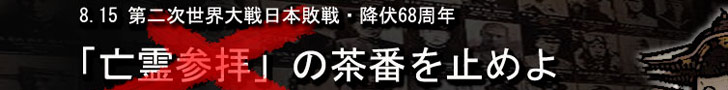




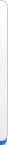
 関連記事
関連記事
 娘に「キャラクター朝食」を作るマレーシアの母親
娘に「キャラクター朝食」を作るマレーシアの母親 日本の平和友好人士が南京大虐殺犠牲者に献花
日本の平和友好人士が南京大虐殺犠牲者に献花 装わずとも美しい「南笙姑娘」
装わずとも美しい「南笙姑娘」 第9回中国(北京)国際園林博覧会
第9回中国(北京)国際園林博覧会



