米自動車産業、日本をレート操作と批判 円安を懸念 (3)
日本の通貨緩和政策の副作用が徐々に現れ始めている。賃金は上がっていないのに、燃料価格や日常生活に必要なものの価格が上がり始めており、一般世帯では家計の負担が増大している。日銀が無制限に国債を購入するとしたのは、長期貸出金利を抑え、企業投資の増加を奨励するのが狙いだったが、実際には日本の株価が大幅に上昇し、資金が債権市場から流れ、国債価格が低下し、国債の利回りが上昇した。また日本の財務省が10日に発表したデータによると、今年3月末現在、国債、借款、政府短期証券を含む「国の借金」は991兆円に達し、国内総生産(GDP)の2倍以上となり、日本人一人当たり平均約778万円の借金を背負っていることになる。日本の財政構造が抱える難問は解決への希望を見いだせないでいる。
米国ハーバード大学のマーティン・フェルドシュタイン教授によると、債務の増大と金利の上昇が合わさると経済的な災難になる。長期金利の急上昇は日本国債の価格を低下させ、世帯資産を目減りさせ、消費支出を抑制することになる。高金利は社債と銀行の貸出に作用を及ぼし、ビジネス投資を抑制するという。
急速な円安は国際社会の懸念も引き起こしている。外部では、日本の新たな通貨緩和政策が大幅な円安をもたらし、他国の対日輸出に影響し、周辺国やその他の地域の経済発展にも影響し、ひいては複数の国が通貨切り下げを競う「通貨安競争」をもたらす可能性があるとの懸念が広がっている。
米財務省のジャック・ルー長官は日本の通貨政策に関心を寄せるとともに、日本は経済活性化の努力において国際合意を慎重に守り、通貨安競争を回避しなければならないと警告する。米国自動車政策会議(AAPC)は9日に発表したコメントの中で、日本政府の円レート操作は米国の自動車産業にマイナス影響をもたらすものと批判した。
あるアナリストの指摘によると、日本の行為に不満があっても、米国や英国などが日本を批判することは難しい。長年にわたり、こうした国々は量的緩和を繰り返して経済を活性化させ、米ドルも英ポンドも通貨安を経験しているからだ。日本はこれらの国よりも「踏み出した一歩が大きかった」に過ぎないという。(編集KS)
「人民網日本語版」2013年5月14日





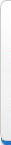






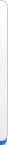
 関連記事
関連記事 四川省什ホウ市 集団で誕生日のパーティー
四川省什ホウ市 集団で誕生日のパーティー 北京什刹海 赤いドレスでジョギング
北京什刹海 赤いドレスでジョギング ブン川地震から5年 祭祀活動
ブン川地震から5年 祭祀活動 英国の億万長者が賭けに負けて女装姿を披露
英国の億万長者が賭けに負けて女装姿を披露



