北斗衛星測位システム アジア・太平洋全域をカバー (2)
衛星による位置の測定には無線伝送技術が必要だ。このため衛星測位システムの建設では周波数が土台となり、運営を保証するものとなる。世界の主要衛星大国は周波数をめぐって激しい競争を繰り広げており、この極めて重要な宇宙戦略資源が不足気味になっている。周波数をめぐる国際的な話し合いを何度も行った後の06年3月、北斗システムの周波数をめぐる取り組みは歴史的な飛躍を遂げた。現在、北斗は国際電気通信連合(ITU)による周波数割り当ての登録リストに組み込まれており、北斗がGPS、GLONASS、GALILEOなどと同等に周波数を保護されていることがわかる。
中国衛星導航(測位)学術年次総会科学院会の副主席を務める北斗衛星測位システム副総設計士の譚述森氏によると、北斗とGDPを合わせて使用すれば、GPSとGLONASSを合わせて使用した時よりも効果が高い。利用者の頭上で稼働する衛星はこれまでの4-6個から現在は8-12個に増加した。北斗が加わったことにより、利用者はより精度が高く、より信頼できるサービスを受けられるようになったという。
中国科学院(科学アカデミー)の院士で北斗衛星測位システム総設計士の孫家棟氏は、「中国は北斗の民間利用市場の育成をただちに加速させ、北斗をめぐる産業の推進を加速しなければならない」とした上で、衛星測位システムの発展には巨額の費用がかかり、単なる軍事利用だけで、民間市場の開発を重視しないとすれば、衛星資源をひどく浪費していることになり、北斗システムの発展や技術的進歩にも影響が出てくる。米国やロシアのように衛星が全地球をカバーしてから民間市場を発展させるというやり方を取れば、宇宙技術の産業化や人材の育成にもマイナスになる。ロシアにはこの点について苦い教訓がある。GLONASSは1996年に稼働し始めたが、民間市場の発展が遅れ、経済的に厳しくなってネットワークを拡大することができなくなったため、信頼できるサービスを提供できていないという。











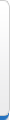
 関連記事
関連記事 ホワイトカラー男性が巨大な「鴨梨」を背負って登場
ホワイトカラー男性が巨大な「鴨梨」を背負って登場 犬の可愛らしい表情
犬の可愛らしい表情 女性スターの真っ赤な唇のメイク
女性スターの真っ赤な唇のメイク 童話のような美しい世界
童話のような美しい世界



