-----過去を振り返ると、このような為替操作による効果は限られている。また米財務省は1年前に、日本の為替操作を非難した。日本は今年、為替操作に対して慎重な姿勢だった。安倍氏本人も為替操作の効果に疑問を呈していたが、なぜ今になり逆の態度を示しているのか。
趙氏:日本経済の最大の問題は高齢化だ。高齢化の進行により、消費の増加率が低下する。日本がいわゆる「失われた10年」に突入した際、日本最大の消費市場は欧米市場・中国市場であった(新興国市場、特にアジアの新興国市場)。しかし現在、欧州と米国は輸出による地域経済の振興を目指している。日本の一部産業は今後、経済構造の調整を図る中国経済との間で摩擦が生じるだろう。日本が中国市場を失った場合、将来的な経済成長はどこに求めるべきか。このような状況下、安倍氏が政治スローガンにより景気刺激策を実現しようとするのも理解できる。しかしその効果についてだが、人為的な為替操作はせいぜい短期的な効果しかもたらさず、経済全体の新興に対する効果は非常に限られている。
-----安倍氏の意思表示が、専門家の懸念を引き起こしている。株式市場、不動産市場、関税のうち、最も大きな影響を受ける分野はどれか。
趙氏:輸入関税は工夫をこらす余地がある。直ちに何かの措置を講じることはないが、間接的に対策を講じるだろう。次の可能性は、人民元相場の上昇だ。日銀が操作をしたからといって、人民元相場が上昇するというわけではない。人民元相場は2005年より上昇傾向にあり、人民元の国際化も進められている。最後の可能性は不動産だ。中国不動産市場は購入抑制策の影響を受けており、円高が不動産市場と必然的なつながりを持つとは限らない。しかし資金流動、不動産業界の発展の特徴に影響を及ぼすだろう。(編集YF)
「人民網日本語版」2012年12月26日
[1] [2]

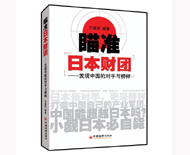

















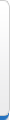
 関連記事
関連記事 性転換者2人が江西省の美人コンテストで優勝と準優勝
性転換者2人が江西省の美人コンテストで優勝と準優勝 新華社が習近平総書記の昔と今の写真を公開
新華社が習近平総書記の昔と今の写真を公開 中国南海艦隊の「海軍の花」
中国南海艦隊の「海軍の花」 哈爾濱氷雪大世界が試験営業 作品2千点以上が登場
哈爾濱氷雪大世界が試験営業 作品2千点以上が登場



