村長「みんなで子育て支える」 支援手厚い富山・舟橋村
【赤田康和】「日本一小さい村」の富山県舟橋村は平成に入ってからの四半世紀の間、人口が増加傾向にあり、15歳未満の子どもの年少人口の全人口に占める割合が21.8%と全国の市町村の中でトップだ。
新年企画では、フェイスブックの「オルタナティブ・ニッポン」で少子化を解決する道を議論中。舟橋村が少子化を回避できた理由は、議論の参考になるかもしれない。金森勝雄村長(69)に話を聞いた。
「宅地開発ができないという規制の網が村全体にかかっていた。いわゆる市街化調整区域だったんです。それが1988年に調整区域から除外された。全国で初のケースだった」。金森村長はこう話す。
水田を埋め立てて宅地にすることが可能になり、89年以降、村営の「東芦原団地」(計75区画)など、住宅団地が次々と造られていった。これまでに累計で約16万8千平方メートルの農地が宅地に転用され、522区画の住宅が誕生した。
人口もぐんぐん伸び、90年の1371人が2010年には2967人まで拡大した。子どもの数も増え、90年に101人だった小学生は2010年には285人に、中学生は53人から109人に増えた。村の平均年齢は38.8歳。
金森村長は「山間部にある村とは違って、富山市という地方都市に近いという地理的特徴もある。それでいて地価が安いから、人が集まった」と話す。
村は、子育てへの支援にも力を入れてきた。生後6カ月から預かる保育所を開設。土曜日も含む週6日、朝7時から夜7時まで預かっている。不妊治療費の助成や乳幼児医療費の無料化を県とともに実施。第3子以降への出産祝い金を村単独で10万円支給している。
衆院選で圧勝し、与党になることが決まった自民党。昨年7月に発表した中長期政策の方向性を定めた報告書「日本再興」では、「0歳児については、家庭で育てることを原則とし、家庭保育支援を強化する」と明記している。
だが、金森村長は「高齢化社会になり、誰もが将来を若い人に支えてもらわないといけない。だから、子どもが育ちやすい環境をみんなでつくり、みんなで子育てを支える。それが原則だと思います」と語る。
子育てを、地域社会が支えるには、地域が人と人とがつながった近所づきあいの人脈網が機能している必要がある。そこで、村は、祭りなどを担う自治会活動に交付金を支給している。98年には、私鉄の駅舎と一体となった村立図書館もオープンさせた。住民1人あたりの貸出数では全国でも上位の利用率を誇る。
村にも課題はある。村の年代別の人口をみると、35-44歳が全体の約2割を占めるのに対して、20代前半は4.3%、20代後半は3.4%しかいない。大学卒業後の若者たちの「Uターン」を促す方策を、役場内にチームをつくって検討する方針だ。
「舟橋村には『村で生まれた子どもたちを自分たちで育てる』という思いがある。昭和、平成の大合併を拒んでおり、伝統的に自立心が強いんです。自治体としても財政は健全で、適正な規模なんです」と金森村長は胸を張る。国立社会保障・人口問題研究所は、舟橋村の2035年の人口は2005年の約1.4倍の3833人になると推計している。
asahi.com 2012年12月19日
Copyright 2012 Asahi Shimbun 記事の無断転用を禁じます。









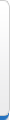
 関連記事
関連記事

 北京で粉雪 雪の見所10カ所
北京で粉雪 雪の見所10カ所 彭麗媛の28年にわたる「春晩」出演をふりかえる
彭麗媛の28年にわたる「春晩」出演をふりかえる 赤ちゃんを演じてストレス解消を図る米英の成人
赤ちゃんを演じてストレス解消を図る米英の成人 北京舞踏学院出身の女性スター
北京舞踏学院出身の女性スター



