 |
| 「静夜思」 |
-----そんな時に昆劇と出会ったわけですね。
そうですね。モダンダンスやジャズダンスはどちらというと身体表現が大きい舞踏なのですが、昆劇の動作は比較的静かで、表現の仕方も大げさではないのですが、逆にその表現の繊細さと深さに深く感動しました。これまで西洋の舞踏に引かれていたので、古典芸能を見るのもその時が初めてで、外国のモダンなものもいいけれど、古典もいいなと認識を改めました。
昆劇は自分に何か違うものを与えてくれるかもしれない、自分はアジア人だし、アジアのルーツを探るのも面白いかもしれないと思って、昆劇「牡丹亭」を習いに中国へ行こうと決意しました。
■昆劇の難しさと奥深さ 見るのとやるのとでは大違い
-----実際に北京で昆劇を習ってみていかがでしたか。
北京の「北方昆劇院」で昆劇を習い始めたのですが、すぐに自分の考えが甘かったことを思い知らされました(笑)。見るのとやるのとではすべてが大違いでした。
まず一つ目は言葉の問題です。昆劇はやはり演劇なので、歌もあれば台詞もあり、動きもあります。まず、歌と言葉につまづきました。実際、15年たった今でも言葉の問題は解決できていません。発音が完璧ではないので、どうしても見る人に伝わらないのです。台詞でも歌を唱っても何を言っているのかわからないという状況になるのが自分でももどかしく一番悔しかったです。
例えば劇で何を伝えたいのか?この役柄はどういう状況で、どういう背景にあるのかなども最初は分かりませんでした。役柄の感情などを理解する術がなかったのです。もう、ただただ、動きを見よう見まねで真似るということを日々繰り返していました。
-----詩吟舞踏や西洋舞踏などをされてきたことで有利なこともあったのでは?
そうですね。動きに関しては、やはり踊りをずっとやってきたこともあり、とにかく先生の振りを見よう見真似で模倣していくという方法で、舞踊の感覚で習っていたのであまり問題はなかったです。先生からも飲み込みが早いと言われました。ただ、やはり言葉の問題が想像以上に大きかったですね。
-----いつから舞台に立ったのですか。
昆劇を習っていた「北方昆劇院」では1年に1度公演を行っていたので、1年目から舞台に立つチャンスをいただきました。最初に演じた演目は、北京に来るきっかけとなった「牡丹亭」でした。主演の杜麗嬢役ではありませんでしたが、杜麗嬢の侍女の春香役を演じました。そのときは、実際の昆劇の役者さんがするのとまったく同じ化粧をして、本物の衣装を着て演じたので嬉しさは格別でした。ただ、思いのほか頭の飾りが重く、メイクで眉を吊り上げるのがとても痛かったことが今でも思い出に残っています。
-----その後、昆劇を習い続けて行くうちに課題も含めて変化はありましたか。
昆劇を習って最初のうちは、演じるのが楽しくて楽しくて仕方ないという感じだったのですが、公演を重ねていくうちに、同じ演目をやる機会が増えてくると、2回、3回と公演を重ねた分だけ進歩がないと駄目だという自分自身へのプレッシャーが次第に増してきました。
実際、自分の中でも進歩があった、なかったというのがわかるようになると次の課題がはっきりと見えてきました。どうやったら観客にこの役柄を伊藤治奈ではなく、役柄そのものとして見てもらえるのか?例えば白蛇伝の青蛇を演じるとしたら、どのようにすれば舞台のそこに青蛇がいると観客に思ってもらえるのかを考え始めました。
でも、頭の中で色々と、この役柄はこう演じたい、踊りたいと思っていても、実際に観客に伝わらないときや模索しても実際に身体で表現しきれないときには挫折を感じました。昆劇も中国の舞踏も、日本人の自分には、身体の条件的にも、語学的にも、演技の限界がありますし、やれる役柄が限定されます。これでは、プロの役者のように演じるのは無理だと感じ日本に帰国しようと考えたことも過去に1度だけあります。
[1] [2] [3] [4] [5]







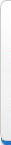






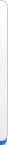
 関連記事
関連記事
 トム・クルーズが北京訪問
トム・クルーズが北京訪問 世界で最もスリル満点の絶叫マシン
世界で最もスリル満点の絶叫マシン 武漢 高齢者1千人がバドミントン
武漢 高齢者1千人がバドミントン グーグルのストリートビュー 「半身のネコ」はいたずら
グーグルのストリートビュー 「半身のネコ」はいたずら



